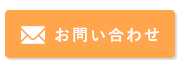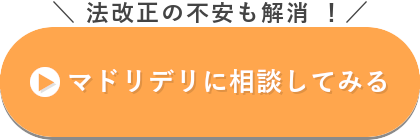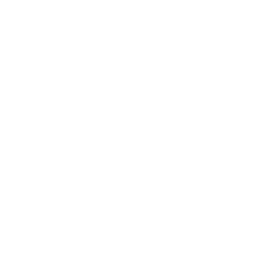準防火地域とはサッシ・外壁・屋根・軒裏に【防火構造】など規制がある
準防火地域とはサッシ・外壁・屋根・軒裏に一定の防火性能が求められる地域です。
準防火地域に木造2階建て住宅(2号建築物、300㎡)を建てると仮定すると、【延焼の恐れのある部分の】 サッシは防火設備、外壁は防火構造もしくは大臣が定めた構造方法、軒裏は防火構造、屋根は全て不燃材料を設置する必要があります。
準防火地域は22条区域より1段厳しい規制がかかります。
サッシ(外壁の開口部)は防火設備
1.開口部には防火窓や防火ドアを設置する必要があります。
2.給排気口にはFD付きの製品等が必要です。給排気口は忘れがちな注意点です。
外壁は防火構造もしくは大臣が定めた構造方法
1.防火構造とは大臣認定を受けた構造です。多くの外壁メーカーから『PC〇〇BE』という認定番号で発売されています。
2.大臣が定めた構造方法とは鉄網モルタル塗やしっくい塗で造る外壁構造です。
鉄網モルタル塗り・漆喰塗りの例
屋内側:9.5mm以上の石膏ボード(真壁構造OK)
屋外側:鉄網モルタル塗りまたは漆喰塗りで塗り厚が20mm以上
という構成になります。
屋根は不燃材料で葺く
一般的に不燃材料の屋根とはレンガ・瓦・アルミニウム・金属板・石などです。ガルバリウム鋼板やスレートが該当します。
また、バルコニーは屋根と同じ扱いになるため、大臣認定の仕上げが必要です。
『DR-〇〇』という認定番号で各メーカーから販売されています。
参照:(屋根) 第六十二条
軒裏は防火構造
軒裏は防火構造とする必要があります。多くのメーカー製品は準耐火構造以上の認定を取得しています。一部認定外の製品に気を付けるだけで問題ありません。
また、軒先の換気金物も大臣認定品を設置する方が安心です。
参照:第百三十六条の二
延焼ライン(延焼の恐れのある部分)とは
延焼ラインは正式には【延焼の恐れのある部分】と言います。
1階では【隣地境界線、道路中心線から3m以下】
2階以上では【隣地境界線、道路中心線から5m以下】の部分です。
設計段階でどこが延焼の恐れのある部分なのか把握し、外壁や開口部に注意します。
準防火地域の調べ方
準防火地域の有無は市町村が公開する都市計画図で調べます。
市町村によって都市計画図はPDFやwebアプリで公開されています。
鴻巣市の場合は両方公開されています。
外壁防火構造とは室内側を含めた【外壁の構成】
木造軸組み工法の場合、外壁防火構造とは単一の外壁材ではなく室内側石膏ボードなどを含む【外壁の構成】全体をさしています。
特に、延焼ラインにかかる浴室や駐車場の室内側に注意が必要です。
使用する外壁材や断熱材の認定番号(PC〇〇BE)の構成に合わせて正しく設計・施工しましょう。
まとめ
準防火地域は細かい部分で法22条区域と違いがあります。【防火構造】を基本として、延焼ラインのサッシ・給排気口に注意しましょう。
マドリデリでは建築確認申請の代行を承っております!
まずはメールフォームよりお気軽にご相談・お問い合わせください。